先日お寺に新年の縁起物のパンフレットが届いており、その中に「屠蘇散」というお屠蘇を作るもとが試供品として入っておりました。新年の準備をするにはまだ少し早い 時期ですが、今回はお屠蘇について書いていきたいと思い ます。
お屠蘇とは
お屠蘇とは複数の薬草を調合した「屠蘇散」という袋を酒やみりんに浸して作る薬酒で、新年最初に飲んでその年の健康と家内安全を願うものです。
お屠蘇の由来
お屠蘇の由来ははっきり定まっていません。中国で唐の時代あたりから飲まれるようになったようで、以下のような説があります。
- 『蘇』は悪⻤の名であり、⻤を『屠る』という意味から『屠蘇』となった
- 昔の中国に屠蘇庵という庵に住んでいる人がおり、その人が毎年除夜に薬包を村の人々に贈っていた。もらった村人がそれを井戶の水に浸し元日に取り上げて酒に混ぜた
日本に渡来したのは嵯峨天皇の時代ではないかといわれております。
お神酒との違い
上記の通り、お屠蘇は新年に飲む薬酒であるのに対し、お神酒は神様にお供えしたお酒で、新年に限らず 1年を通して飲まれます。ちなみに、お屠蘇にもお神酒にも飲む順番があり、お屠蘇は年少者から年⻑者の順番で飲み、お神酒は年⻑者から年少者の順で飲みます。
お屠蘇の作り方
古来は屠蘇散を除夜に井戶の水に浸し、元日に取り出して酒と混ぜて飲んだそうです。みりんが普及しだした江戶時代頃からは酒の代わりにみりんを使っていたようです。 そのため、現代でもお屠蘇は本みりんを使います。本みりんに屠蘇散を入れ、4時間ほど浸けたのち屠蘇散を引き上げます。家で飲む際には大晦日寝る前に屠蘇散を本みりんに入れ、起きたら引き上げるくらいでよいでしょう。本みりんだけでは甘すぎるという方はお好みで日本酒も混ぜると甘みがやわらぎます。
みりんについて
お屠蘇に入れるみりんは本みりんを使ってください。みりん風調味料や発酵調味料(料理酒)などは塩分が含まれておりあまりお勧めできません。また、本みりんは米由来の甘みのみで調味料が一切入っていないのに対し、みりん 風調味料などはショ糖や水あめなどで人工的に甘みがつけられているため、本みりんのほうが甘さがなめらかで飲みやすいようです。
金剛寺は除夜のお参りでお屠蘇を振舞っています!
金剛寺は今年より除夜の鐘のお参りを夕方に行います。年をまたいでお参りができるのが一番理想的なのですが、夜中の参拝に支障をきたすことが増えているためお参りの時間帯を夕方にずらしました。
本年は本みりんで作ったお屠蘇(アルコールを飛ばしたお屠蘇も併せて)もご用意させていただく予定です。一年の感謝を込めてぜひお参りにいらしてください。今年身内に不幸があった方もお寺でのお参りは全く問題ありませんので、お礼参りと初詣を兼ねてお参りにお越しください。
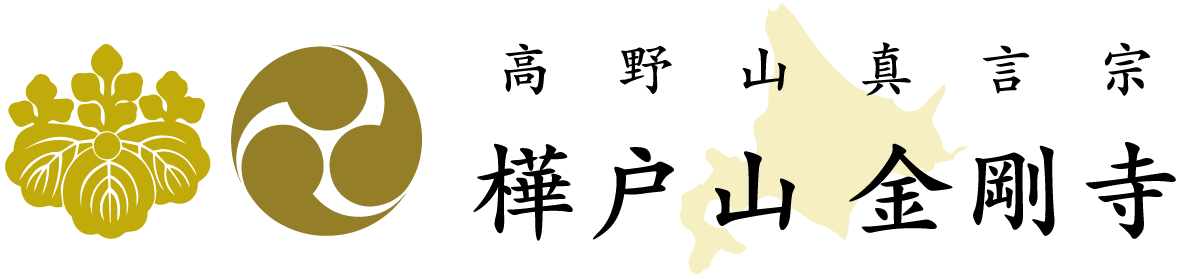






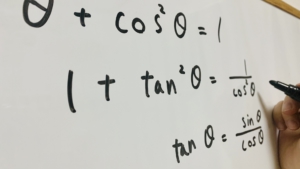

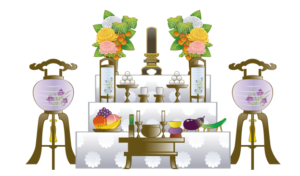

コメント