葬儀の方向性を決めるのはだれか
「故人の遺志により社会福祉法人に・・・を寄付しました」
「故人の遺志により葬儀を先に行わせていただきました」
人が亡くなる場面においては「故人の遺志」という言葉が使われることがあります。近年では「エンディングノート」を作成し伝えたいことを事前にまとめておく方も増えてきているようです。
残された側からしても、『故人の遺志』が残っている方がその方の思い通りに死後の整理ができたという気持ちが起こり、心の整理がつきやすくなるため、『故人の遺志』を遺すことは本人にとっても遺族にとっても非常に重要なことです。
故人の遺志の本意はどこにあるのか
ただし、『故人の遺志』をくみとる側は一点だけ留意しなければいけない事があります。それは葬儀の形式をどうするか、についてです。近年、故人の遺志により『簡素な葬儀』を行うケースが増えつつありますが、その遺志を額面通り受け取るべきかどうかは熟慮すべき点ではないでしょうか。
たとえば、仲の良い友人がどこか遠いところに引っ越す場合を考えてみてください。その友人が「引っ越しの時は見送りもいらないし、餞別も何もいらないよ」と言ったとします。あなたはその友人の言葉通り見送りや送別会もせず、餞別も渡さず、何事もなかったかのように過ごすでしょうか。おそらく多くの人は何らかの行動を起こすはずです。
死によって起こる別れと、現実世界での別れとでは、その相手に対する接し方はそこまで大きく隔たりがあるものでしょうか。葬儀の時だけ旅立つ人の言うことを額面通り受けとめて実行すべきなのでしょうか。
勿論、特殊な事情がありそうせざるを得ないケースもあるでしょう。しかし、故人が「遺族に過度な負担をかけないため」という気遣いから遺してくれた言葉を額面通りに遺族が実行としたら、それを知った故人は少し寂しい気持ちになるかもしれません。
(ただ、死んだ後のことはどうでもよいので簡素にしてほしいと本当に要望する方もいますが、その点については後述の直葬の部分でお話いたします)
簡素な葬儀とはどんな葬儀?
『簡素な葬儀』という言葉には大きく分けて2つの意味があります。1つは葬儀はきちんと行うものの費用をあまりかけない葬儀、という意味。もう1つは、葬儀の儀式自体を省略し、遺体の処理を行うだけにするという意味です。乱暴な表現になるかもしれませんが、①『質素な葬儀』と②『時間とお金を節約する葬儀』どちらの場合も簡素な葬儀と表現されます。
②の葬儀を行った場合、故人が火葬されるまでの間に関係者に連絡がいくことはあまりありません。周囲のお世話になった方への連絡を省略しているのであって簡素にしているわけではないのです
。そもそも、簡素に葬儀を行うことを検討するならば、施設・設備面でかかる費用を必要最低限にとどめることを検討すべきでしょう。最近は遺族の手間やご近所の手を借りなくてもよいということから、規模の大小を問わずセレモニーホールで行うことが多いですが、費用的な問題がどうしてもあるようでしたら自宅、寺院、公民館などの選択肢を考えてもよいかもしれません。手間や利便性の面では専用のホールに劣ることが往々にしてあるかと思いますが、費用面の問題は解決できる場合が多いかと思います。
故人亡き後、故人に代わってお世話になった方々へ連絡しお礼を申し上げるのは遺族の重要な役割だと考えます。「親戚がみな遠方にいる」「親族、知人が高齢になっている」という理由で関係者に気を遣わせないように家族葬を選択する場合もあるようですが、葬儀に足を運ぶかどうかはその知らせを受けた人が判断することであり、遺族側が判断することではないのです。
実際の例として、葬儀を家族葬で済ませ、故人の知人・友人に亡くなったことを後日知らせたところ、半年近くいろいろな人が弔問にやってきたという話をされていた遺族の方もいます。その遺族の方は、こんなことならお世話になった人たちに故人の死を知らせて葬儀を行った方が良かったと悔やんでいらっしゃいました。
遺族の葬儀における重要な役割の一つは、お世話になった人々に故人の死を周知し生前のご厚意に感謝の意を表することだと私は考えます。故人と関係のあった方々とお話ししていくうちに今まで見えていなかった故人の一面がうかがえるケースも多々あります。故人のことをより知るためにも関係者に連絡し生前の厚意にお礼を申し上げることは大切なことなのです。
直葬は、故人にとっても遺族にとっても良くない結果を生む
『簡素な葬儀』の中でも最も簡素な葬儀として直葬という方法をとる方も増えてきているようです。「死んだら終わりなんだから葬儀もせずにすぐ火葬場で焼いて骨はそこら辺にでも撒いてくれればいい」という方も中にはいらっしゃいます。この場合は葬送儀礼すら省略されるわけですが、『故人の遺志』であれ遺族の意思であれ、故人の身元引受人がいて特殊な事情がないにもかかわらず直葬が選ばれてしまうということは、故人にとって、というよりも遺族にとって不幸という他はないです。死後自分がどのような弔われ方をするかは自らの生前の行いが色濃く反映される可能性が非常に高いと思われますので、故人にとってはある程度やむを得ない結果といってもいいのかもいしれません。しかし、肉親の死に対してすら悲しむこともなく無関心になれるように育ってしまった子供(遺族)はある意味被害者といってもよいのではないでしょうか。その遺族の考え方を作り出した原因がすべて故人(親)にあるとはいえませんが、その故人が与えた影響は大きいかもしれません。そしてその『無関心』は孫やひ孫にもずっと伝わっていく可能性があるだけでなく、その人にかかわった他人にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
『おかげさま』の気持ちを忘れない
『個人主義』という考え方が日本人の中に間違った形で入り込んで定着してしまった結果、現代の日本人は個人主義を『他人のことよりも自分のことを優先すること』や、『自分に悪影響が及ばなければ他人のことには関与しない』という意味で解釈する人が多くなっている気がいたします。そして、『自分』という人間が、過去も現在も未来も独立して存在しうるかのような認識を持ってしまう傾向があるように感じます。このような考え方が自分さえよければ他人はどうでもよい、という他者への無関心へつながっているのではないでしょうか。
この世に生を享ける時も、この世で生活をしている間も自分以外のモノや人がいなければ『自分』が存在し生命を維持することは不可能です。何もないところから突然『私』という人物が赤ん坊の形をして発生して、体外から食物・水分一切のものを摂取することもなく誰の手も借りずに成長し死んでいくような人などいるはずがないのです。さらに言えば死んだ後も自らの肉体の処理に関して必ず誰かの世話にならなければならないはずです。我々はこの事実を常に思い起こし、他者があってこその自分であるという考えに立ち返り、『おかげさまで』という他者への感謝の気持ちを持ち続けることが重要なのではないでしょうか。
村八分ということばがありますが、これはある集団の中で仲間外れにされることを意味します。『八分』という言葉がなぜ仲間外れという意味の中に使われているかというと、昔の人はある事柄の発生した時だけは仲間外れのものでも仲間に迎え入れていたからです。その二分とは、火事と葬儀でした。
『お互いさま』という気持ちがどこかにあるから普段は許すことができない人であっても、葬儀の時にはわだかまりを超えて皆が協力してくれたのです。
葬儀は亡くなった人の為であるのはもちろんのこと、残された者たちの為でもあります。亡くなった方が死後仏道修行に励めるようお膳立てをすること、お世話になった人々へお礼の気持ちを伝えることは遺族の役目ですし、亡くなった人の肉体が遺骨へと変わっていく様を儀式の中で見守っていくことで、遺された人は死を実感し徐々に気持ちの整理をしていかなければならないのです。
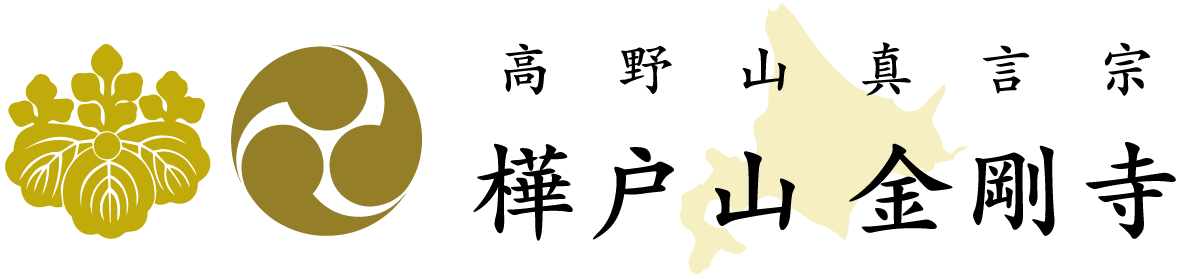







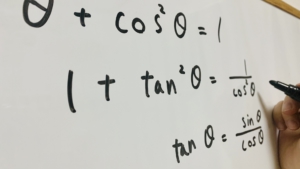

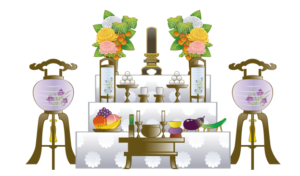
コメント